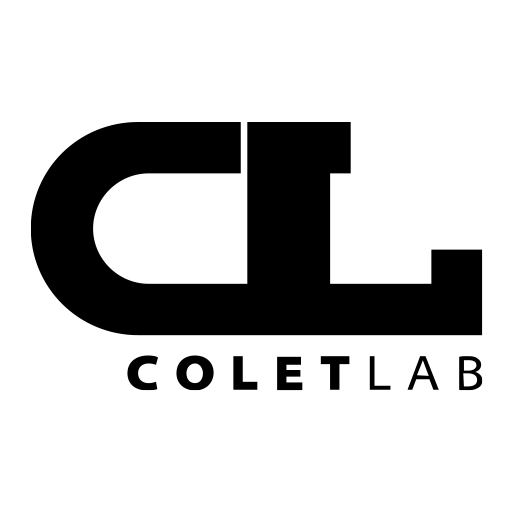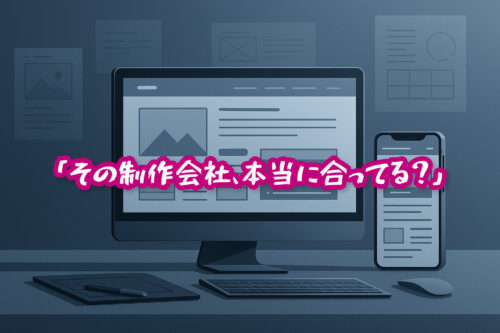ホームページ制作会社の選び方ガイド【比較・費用・注意点】
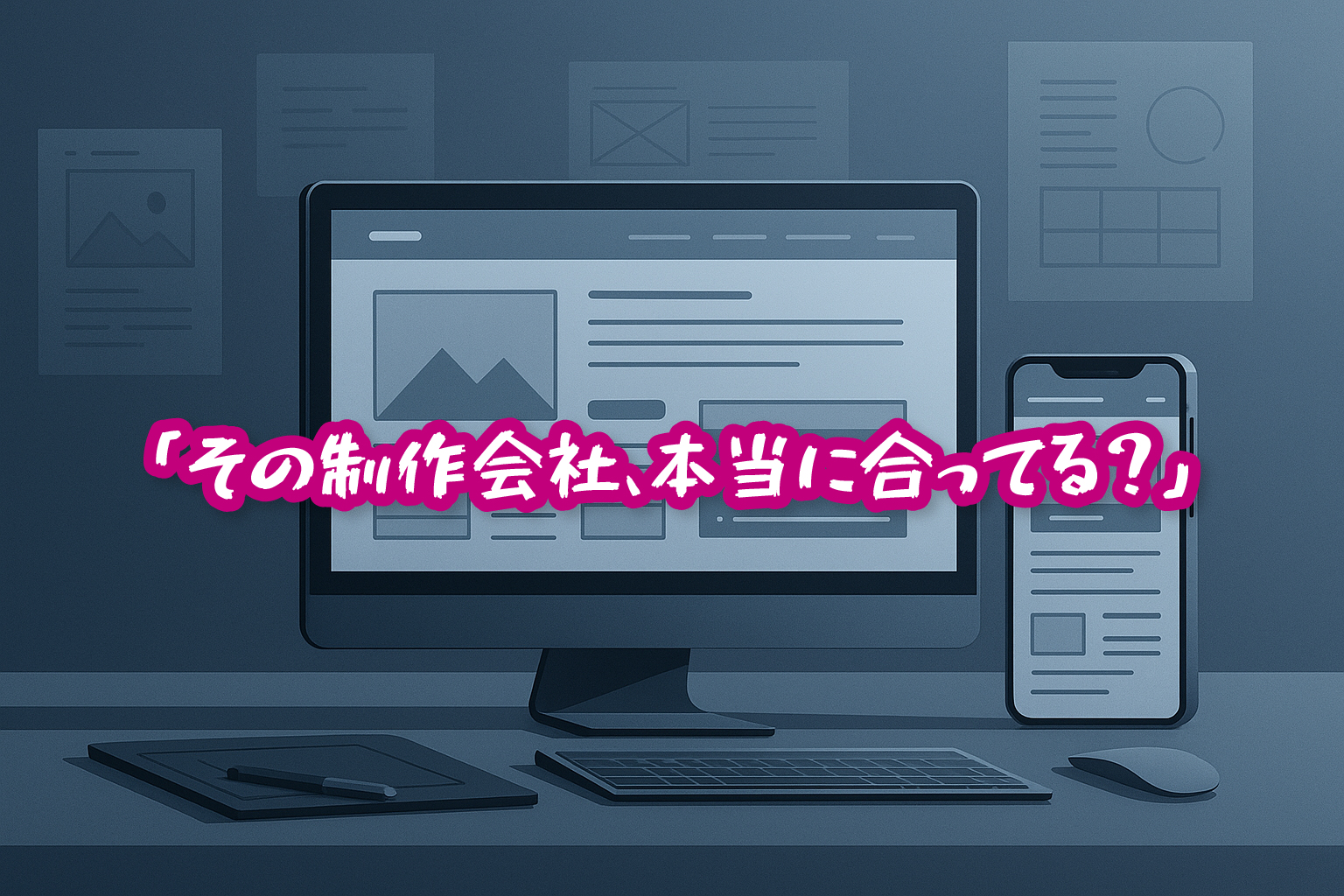
「どこの会社に頼めばいいのか、正直わからない」
「なんとなく高そうで、相談するのも気が引ける」
「地元の会社と東京の会社、どっちがいいんだろう?」
ホームページ制作の相談を受けていると、こんな声をよく聞きます。
一見デジタルな話のようでいて、選ぶ相手は「人と会社」。だからこそ、判断が難しいんですよね。
でも、安心してください。
この記事では、自社にぴったりの制作会社を選ぶためのチェックポイントを、実践ベースで整理しました。
- 制作会社のタイプごとの違い
- 相場と費用の中身
- 相談前に整理すべきこと
- 失敗しないためのチェックリスト
まで、「いま何を考えるべきか」が一目でわかるようにまとめています。
読むだけで、「ホームページ制作会社の選び方」がクリアになるはずです。
では、いきましょう。
ホームページ制作が「悩ましい案件」になりやすい理由
ホームページ制作って、実はややこしい買い物なんです。
なぜなら、以下のような「選びにくさ」が重なっているから。
選びにくい理由トップ3
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 比較がしにくい | 会社ごとに料金体系・仕様・サポート内容がバラバラ |
| 決め手が分かりにくい | 見積書を見ても「どれがいいのか」が判断しづらい |
| 作った後が読めない | 公開後にどんな運用が必要か、イメージしにくい |
「とりあえず作ってみよう」と勢いで進めると、
- 納期が延びる
- 修正のたびに追加費用
- 検索にまったく出てこない
といった“あるある”に直面します。
さらによくあるのが、「安さにつられて頼んだ結果、最低限の機能しかないサイトになった」パターン。
「安かったけど、問い合わせフォームもGoogleマップもついてなかった…」なんて話も。
制作会社を探す前にやっておくべき3つの準備
実は、制作会社を選ぶ前にやっておくとスムーズになることがあります。
この3つ、意外と見落としがちですが超重要です。
① ホームページを作る目的を明確にする
ホームページって、ただの名刺代わりじゃありません。
なにかしら「成果」を出すためのツールです。だから、目的の明確化は第一ステップ。
| よくある目的 | 目的の内容 |
|---|---|
| 問い合わせを増やす | サービスへの導線設計やフォームの強化が必要 |
| 採用を強化したい | 求人ページの設計や社員紹介の工夫が必要 |
| 店舗集客につなげたい | 地図・MEO・スマホ対応が重要 |
| 信頼性アップを狙いたい | デザインや写真のクオリティが肝 |
目的がボヤけていると、出来上がったサイトもどこかぼやけた印象になります。
② 必要なページ構成をイメージしておく
「トップページとお問い合わせがあればいいでしょ?」
…と思いきや、それだとユーザーはなかなか動いてくれません。
以下のような構成があると、成果が出やすくなります。
| ページ名 | 内容 |
|---|---|
| トップページ | キャッチコピー・強み・主な導線 |
| サービス紹介 | 商品やサービスの詳細説明 |
| 会社概要 | 住所・代表者・沿革など |
| お問い合わせ | フォームや電話番号の記載 |
| よくある質問 | 説明負担の軽減につながる |
| ブログ・お知らせ | 最新情報の発信・SEOにも有効 |
もちろん全部必要ではありませんが、「必要最低限+α」は意識しましょう。
③ 予算の目安を決めておく
「いくらかかるか分からないから聞けない…」
という声もよくあります。でも、ざっくりでもいいんです。
「この範囲なら出せる」という上限があるだけで、相談がスムーズになります。
ホームページ制作会社にはどんなタイプがある?
ここからは、制作会社の分類と、向いている人の傾向を見ていきましょう。
ざっくり分けると、以下の4タイプがあります。
制作会社のタイプと特徴
| 種別 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 地域密着型 | 対面相談がしやすく、地元企業に詳しい | 個人店舗・地域ビジネス向け |
| 大手・全国対応型 | 実績豊富で法人対応に慣れている | 中堅〜大企業や官公庁向け |
| フリーランス | 柔軟で比較的安価、個人対応が得意 | 初期費用を抑えたい方 |
| 格安テンプレ系 | 短納期・低価格、機能は最小限 | とにかくWebが必要な方 |
ポイントは、「価格の安さ」ではなく「目的との相性」です。
「安かったけど成果ゼロ」では意味がありません。
「自社に必要な機能・支援が得られるか」で判断しましょう。
制作費用の相場と、落とし穴の見抜き方
「相場感がわからない」という方のために、ざっくりとした目安を紹介します。
制作費用の相場感(税抜目安)
| サイト規模 | ページ数 | 費用目安 |
|---|---|---|
| ランディングページ | 1ページ | 約10万〜30万円 |
| 小規模サイト | 5〜8ページ | 約30万〜80万円 |
| 中〜大規模サイト | 10ページ以上+CMS導入 | 約80万〜200万円 |
| ECサイト | 商品管理・決済機能つき | 100万円以上〜 |
「安すぎる制作」のよくある落とし穴
- 修正回数が制限されている(例:3回まで)
- テキストや画像はすべて自分で用意
- SEO対策やスマホ対応が含まれていない
- サーバーやドメインが別料金
- 公開後の更新や相談に対応してくれない
「初期費用が安い=総額も安い」とは限りません。
見積もりでは「何が含まれていて、何が別料金か」をしっかり確認しましょう。
地元 vs 都市部、どっちに依頼すべき?
「近所の会社に頼むべきか、東京の制作会社に頼むべきか」
この質問、実はすごくよく聞かれます。
地元制作会社のメリット
- 顔を見ながら相談できて安心感がある
- 地域の商習慣や業界特有の事情に詳しい
- 比較的リーズナブルな価格帯が多い
都市部制作会社のメリット
- 幅広い業種での実績がある
- 専門チーム体制での対応が可能
- 大規模・複雑な案件にも慣れている
おすすめは、「まずは地元で相談、相見積もりで比較」というステップ。
とくに初めての制作なら、顔の見える距離でのやり取りが安心です。
失敗しないためのチェックリスト
いざ相談・契約となると、「どこを見ればいいの?」と不安になりますよね。
そんなときは、以下のチェックリストを使ってください。
制作会社チェック項目
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 実績 | 自社と似た業種・目的のサイトがあるか |
| デザインの傾向 | 自社の雰囲気にマッチしているか |
| スマホ対応 | モバイルでも見やすくなっているか |
| SEO設定 | GA4やサーチコンソールの設定をしてくれるか |
| 保守サポート | 公開後の相談や更新対応があるか |
| 担当者の対応 | 質問に丁寧に答えてくれるかどうか |
ちょっとしたテクニック
「画面共有で操作説明してもらえるか」も確認しましょう。
これがあるだけで、運用の不安がグッと減ります。
ここまで紹介した対策は、すぐにでも取り組めるものばかりです。
もし「全部は難しそう…」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
継続することで見えてくる、本当の成果
ホームページ制作って、実は公開後こそが本番です。
どんなにデザインがよくても、情報が古ければすぐに信頼は失われます。
でも、逆に言えば――
更新し続ければ、信頼も集客も“勝手についてくる”状態が作れるということ。
継続的な運用で得られる成果
| 項目 | 変化・効果 |
|---|---|
| 情報更新 | 最新情報が信頼感につながる(例:営業時間・新メニュー) |
| ブログやお知らせ | 検索に引っかかるキーワードが増える=SEOに有利 |
| 採用ページの更新 | 社風や働き方を発信することで、ミスマッチを防げる |
| 事例・実績の追加 | 導入事例が新たな見込み客を呼び込むフックに |
「毎月なにか書かなきゃ…」と思うと面倒に感じるかもしれません。
でも、“仕組み化”すればラクになるのがWebのいいところ。
運用の仕組み化アイデア
- 毎月1回、Googleカレンダーで「更新日」を決める
- 週1回の社内ミーティングで「最近の変化」をメモする
- 担当者が不在でも回るように、マニュアルや手順書を作っておく
こうして運用が“日常化”すれば、
「気づいたらアクセスが伸びていた」なんてことも珍しくありません。
アクセス解析ツールの基本設定を忘れずに
どれだけ更新しても、効果測定ができなければ改善もできません。
だからこそ、以下の2つのツールは最初に設定しておくのがおすすめです。
Googleアナリティクス(GA4)
- サイトにどれくらい人が来ているか
- どのページがよく見られているか
- どんなデバイスや地域から来ているか
といった情報がわかる、無料のアクセス解析ツールです。

Googleサーチコンソール
- どんな検索キーワードでサイトに来ているか
- どのページが検索結果に出ているか
- インデックスの状況(=Googleに登録されているか)
が分かります。SEOの改善にも欠かせないツールです。

設定手順(簡易版)
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① Googleアカウントを用意 | できれば業務用アドレスで登録を |
| ② GA4に登録 | プロパティを作成 → タグをheadに貼る |
| ③ サーチコンソールに登録 | 所有権確認 → サイトマップ(sitemap.xml)送信 |
慣れていない場合は、制作会社に「設定まで依頼できますか?」と聞いてみましょう。
それだけで、公開後のスタートダッシュが大きく変わります。
※GA4については、Google Analyticsの公式ガイドも参考になります。
ホームページ×Googleビジネスプロフィールで集客力を倍増
最近の傾向として、「ホームページ単体」よりも
Googleビジネスプロフィールとセットで運用する企業が増えています。
なぜビジネスプロフィールと連携すべきか?
- 検索結果に表示されやすくなる(ローカルパック)
- クチコミが見られるので信頼につながる
- 「プロフィール→ホームページ」への導線ができる
つまり、リアルな声と、しっかりした情報の両方を見てもらえる状態が作れるんです。
具体的な連携の方法
| 対策内容 | ポイント |
|---|---|
| プロフィールの最新情報を保つ | 営業時間や定休日をこまめに更新 |
| クチコミを集めて返信する | 信頼感アップ&検索評価にも好影響 |
| ホームページとリンクする | 双方向の導線で回遊率がアップ |
「ビジネスプロフィールの登録って面倒じゃないの?」という声もありますが、
Googleビジネスプロフィールの公式ページでは初心者向けに丁寧な手順が掲載されています。
手順通りに進めれば、15分もあれば完了します。

契約時に「これだけは確認しておくべき」こと
どれだけ信頼できそうな制作会社でも、契約内容はしっかり確認すべきです。
トラブルの多くは、「聞いてなかった…」という認識ズレから発生します。
契約前にチェックすべき4つのポイント
| 確認項目 | 理由 |
|---|---|
| 納品形式(データの所有権) | 解約後もサイトを使えるかどうか |
| 月額費用の有無 | 保守・更新・サーバーが含まれているか |
| 修正対応の範囲 | 回数制限・対応期間に要注意 |
| 契約期間の縛り | 最低契約期間が設定されていないか |
特に「サブスク型の契約」は、月額が発生する代わりにサポートが含まれていたりします。
「安い!」と感じても、長期的に見て総額はいくらになるのか?を冷静に見極めましょう。
今、必要なのは「自社に合う一社」を見つけること
ホームページ制作会社って、数だけ見れば星の数ほどあります。
でも、選ぶべきは“有名な会社”じゃありません。
自社に合う会社を選ぶ基準
- 「集客を強化したい」なら、マーケティングに強い会社
- 「採用を増やしたい」なら、求人ページに力を入れている会社
- 「ブランディングがしたい」なら、写真・デザインが得意な会社
つまり、「何を実現したいか」さえはっきりしていれば、選び方は自然と見えてくるんです。
自分で運用する場合の壁も知っておこう
ここまで読んで、「自分でもやってみよう」と思ってくださったならうれしい限りです。
でも、正直に言えば、継続はなかなか大変です。
- 担当者の異動や退職で更新が止まる
- アクセス解析を見ても改善に活かせない
- 気づけば「作ったまま」のサイトに…
こうした状態を防ぐには、仕組み化・継続化・再現性のある支援が必要になります。
「45分で課題が見える」無料診断をご活用ください
「今のホームページ、これでいいのか?」
「そもそもWebマーケティングって何から見直せばいいの?」
そんなモヤモヤを感じている方は、ぜひ弊社の無料Webマーケティング診断をご活用ください。
- 現在のホームページの課題
- 集客・問い合わせにつながる導線設計
- Googleビジネスプロフィールの活用方法
- 今後改善すべき具体アクション
を、たった45分のヒアリングで見える化します。
株式会社コレットラボでは、ホームページ制作はもちろん、
Web集客・SEO・MEO・LINEマーケティングまでトータルで支援しています。
- 全国対応
- オンライン診断OK
まずは「相談だけ」でも大歓迎です。
気負わず一度、無料診断を受けてみてください。
▶ 45分の診断であなたのWebマーケの課題を明確に。無料Webマーケティング診断はこちら
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
この記事が、あなたのホームページ制作の一歩を後押しできたなら幸いです。